日本テレビ系の『世界の果てまでイッテQ!』がすごい。
番組開始10周年となった先の2月の視聴率は、5日が22.5%(関東平均/以下同)、12日が22.2%、19日が20.8%、26日が19.9%と超高値安定。月の平均視聴率21.7%は番組歴代最高という。10年目を迎えて金属疲労どころか、ますます快調である。
思えば、昨年10月に民放他局が軒並み日曜日のゴールデン帯に新番組をぶつけた、いわゆる“日曜ゴールデン戦争”。迎え撃つ王者日テレもうかうかしていられないと思ったものだが――蓋を開けてみれば、『ザ!鉄腕!DASH!!』も『イッテQ!』も、むしろ以前より視聴率を上げている。
要は、ネットニュースなどで日曜ゴールデン戦争を知った新規の視聴者たちが一通りザッピングをした結果、日テレを選んだんですね。それは、裏番組たちが今年に入って一段と視聴率を下げたことからも推察できる。フジの『フルタチさん』は先の2月26日に番組最低となる4.0%を記録し、TBSの『クイズ☆スター名鑑』に至っては、知らないうちに1月で終わっていた。
日テレの強さの秘密 昨年、日テレは3年連続「年間視聴率三冠王」を達成した。そして今のところ、その勢いに陰りはない――。
なぜ、日テレはそんなに強いのか。
同局の強みは、先に挙げた日曜日の番組ラインナップをはじめとするバラエティだ。現在、地上波のプライムタイム(19時~23時)の番組の実に8割近くがバラエティ。要は、バラエティを制す局がテレビ界を制すということ。
そう、日テレが強いのは、日曜日だけじゃなく、他の曜日もバラエティがとことん強いからなんですね。最近は月曜日もかなり強力で、『有吉ゼミ』から『世界まる見え!テレビ特捜部』、『人生が変わる1分間の深イイ話』、『しゃべくり007』に至るラインナップは他局を寄せ付けない。フジの月9がピンチなのも、『SMAP×SMAP』の後番組が絶望的に苦戦しているのも、そういうことだ。
いや、火曜日だって『踊る!さんま御殿!!』と『幸せ!ボンビーガール』が相変わらず強い。水曜日だって鉄板の『ザ!世界仰天ニュース』がある(4月から火曜日に移行)。木曜日だって『ぐるナイ』に『秘密のケンミンSHOW』、金曜日だって――あーキリがない。とにかく毎日、安定して二桁稼げるバラエティが揃っているのが日テレの強み。
それらの番組が安泰な限り、日テレの天下は続くのだ。
ドラマも日テレ とはいえ、バラエティばかりが際立つと、局のイメージとしてどうなのかという話にもなる。キャバクラで番組名を出しても若い女性にモテないかもしれない――なんて日テレの人たちが考えたのか知らないけど、実は日テレ、近年はドラマもそこそこ強いんですね。
現在、同局はプライムタイムに連ドラ枠を3つ持っているけど、このうち特に強いのが、水曜10時枠だ。同局の櫨山裕子プロデューサーが開拓した、いわゆるアラサー女性の応援枠。過去に『光とともに…~自閉症児を抱えて~』や『ハケンの品格』、『ホタルノヒカリ』、『Mother』、『家政婦のミタ』、『花咲舞が黙ってない』――などヒット作を連発。昨年も『世界一難しい恋』、『家売るオンナ』、『地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子』と、平均二桁視聴率を3つも輩出した。
昨今、一桁ドラマが多い中、この安定感はたいしたもの。今や同枠はTBSの日曜劇場、テレ朝の木曜ドラマと並ぶ「3大連ドラ枠」とも呼ばれる。
朝も昼も安泰 そうそう、朝帯も日テレは強い。昨年、『ZIP!』が、それまで同時間帯の年間視聴率トップの座を8年間守り続けたフジテレビの『めざましテレビ』を抜いて、遂に年間首位の座に就いた。
前番組『ズームイン!!SUPER』から大胆に衣替えして、2011年にスタートした当初はライバル『めざまし』に大きく差を開けられていたけど、6年かけて追い付き、追い越した形だ。帯番組は習慣視聴。しばらく、この傾向は変わらないと思われる。日テレの視聴率はここでも安泰というワケ。
一方、昼帯に目を向けると『ヒルナンデス!』があるが、こちらはフジの『バイキング』が昨年4月に“生ホンネトークバラエティ”に衣替えして視聴率が上昇し、目下、TBSの『ひるおび!』を加えた三つ巴状態である。
だが、ライバル2局が時事ネタで競い合っているのを横目に、『ヒルナンデス!』は独り、バラエティ路線。ある意味、傍観者の立ち位置だ。そう、ここでも日テレは安泰なのだ。
王者日テレの未来を占う ――そんな次第で、朝も昼も夜も、今のところ王者日テレに死角はない。
でも、過去のテレビ界を見ても、かつてのTBSやフジテレビがそうだったように、永遠に王者であり続けるテレビ局などない。現に日テレ自身も90年代の全盛期から一転、21世紀に入って一度低迷した歴史がある。
そう、現在の日テレも、未来永劫安泰である保証はない。そうでなくても、今やテレビ界はスマホやネットに押され、ピンチなのだ。
この先、日テレはどうなるか。
それを占うには、温故知新――やはり同局の歴史を紐解くのが一番だろう。そう、歴史は繰り返す。
少々前置きが長くなったが、今回は日テレの歴史を振り返りたいと思う。しばし、お付き合いのほどを。
日本初の民間テレビ局 このコラムを読んでいる人なら大抵知ってると思うけど、日テレは日本初の民間テレビ局である。開局したのは、1953年8月28日。とはいえ、そこに至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。
話は、その3年前にさかのぼる。
柴田秀利なる一人の男がいた。この御仁、かつて読売新聞でGHQ担当の記者を務め、その後GHQに雇われ、1950年当時はNHKのラジオでアメリカのニュースを日本向けに翻訳して紹介するキャスターを務めていた。GHQは日本人をアメリカナイズしようと考えていたのだ。
そんな柴田氏の日課は、毎日、アメリカから入電される膨大な新聞記事に目を通すこと。ある日、彼はカール・ムントなる上院議員が唱える「ヴィジョン・オブ・アメリカ」なる記事を見つける。
それが――その後の日本のテレビ史を大きく変える記事であった。
カール・ムントの構想 カール・ムントはアメリカの上院議員である。1950年6月5日、上院本会議で彼はこう演説した。
「今日の冷戦時代においては、イデオロギー情報戦略が重要になる。私は、自由主義陣営における海外のテレビ網の構築を提案したい。例えば、日本では東京の大放送局と、全国22カ所の中継局によって、そのサービスを提供できる。マッカーサー将軍下の占領軍は、自由の教訓と民主主義の概念を映像によって速やかに、日本全国に送り届けることができるだろう」
――既に、この時点でアメリカはテレビが大衆に及ぼす力を見通していたんですね。外電を読んだ柴田氏は、古巣である読売新聞社主の正力松太郎のもとを訪ねる。そして、ムント構想を伝え、こう提案した。
「この『ヴィジョン・オブ・アメリカ』の構想を、アメリカと組んで正力さんが実現しませんか?」
正力松太郎の先見性 正力松太郎――。言わずと知れた、日本の民間放送の扉を開いた人物である。
そのキャリアは、東京帝大を卒業して内務省に入り、エリート警察官僚としてスタートする。しかし、警視庁警務部長時代に、皇太子(後の昭和天皇)が暴漢に襲われる「虎ノ門事件」の責任を負い、懲戒免官に。そこへ救いの手を差し伸べたのが、かの後藤新平だった。
後藤の援助で、正力は弱小紙の読売新聞を買収する。そこから彼は、類い稀なる経営センスを発揮し、同紙の部数を伸ばしていく。他紙がどこもやらなかったラジオ面を創設したり、アメリカからベーブ・ルースら大リーグを招聘して親善試合を催したりと、数々のアイデアを仕掛け、いつしか読売新聞は、朝日や毎日と並ぶ全国紙になっていた。
戦後は戦争責任を問われ、一時巣鴨プリズンに収監されるも、47年9月に出所。読売新聞の経営に戻り、奇しくも次の一手としてテレビ事業を模索していた。柴田氏が訪ねてきたのは、まさにそのタイミングであった。
テレビ開局の予告 1951年元旦、読売新聞は大きく社告を載せる。
「テレビ実験放送開始、都内に常設受像機、地方も巡回」――それは、マイクロウェーブを使って、東京を中心に22のネット局で全国を結ぶ民間放送の開局を予告するものだった。ムント構想そのものである。
当時は、朝鮮戦争の真っ只中。アメリカは「反共」政策の最前線基地として、世論形成のための日本のテレビ網の構築を急いでいた。それには、既存の公共放送のNHKではなく、自分たちがコントロールしやすい民間放送がいい。
そんなアメリカGHQ側の思惑と、テレビ事業に関心のある正力氏との思惑が合致し、異例の早さで開局準備が進んだのである。
NHK対日本テレビ 1951年8月。正力氏は新会社の社名を『日本テレビ放送網』と決定する。それは、ムント構想の『THE JAPAN NATIONAL NETWORK COMPANY』をそのまま訳したものだった。そして同年10月2日、電波監理委員会に放送免許を申請する。慌てたNHKはその3週間後に申請書を提出した。
ここから、日本テレビとNHKとの間で、熾烈な開局レースが始まる。日テレにはGHQや米電機メーカーのRCAがついた。一方のNHKには、テレビの父・高柳健次郎氏や国産の電機メーカー陣が後押しした。
52年7月、日本テレビに予備免許が下りる。NHKは留保となり、日本テレビが国内テレビ第一号となった。
だが、ここからNHKの猛烈な巻き返しが始まる。遅れること4カ月、12月5日に予備免許が下りると、一気に開局へ向けて動き出す。一方の日テレは、アメリカ本土のテレビ局の開局ラッシュと重なり、米RCA社の送信機が品不足に陥ったことから開局作業が滞る。
結局、開局レースは翌53年2月1日にNHKが制した。
日本テレビ開局 NHKに遅れること7カ月、1953年8月28日午前11時20分、日本テレビが開局した。吉田茂首相を招いての開局式に続き、舞踊『寿式三番叟』の上演。だが、真の目玉はその後だった。正午を知らせる精工舎(現・セイコーホールディングス)のCMが流れたのである。そう、日本初のテレビCM。これこそNHKにはない、日テレ独自の放送だった。
但し、技術のミスで、フイルムは裏返しで放送され、音声も流れなかったという。日本初のテレビCMは、日本初の放送事故でもあった。
ひとまず開局した日本テレビ。時に、朝鮮戦争は前月に終結しており、当初GHQが目論んだ世論誘導の必要性はなくなっていた。代わって日テレに重くのしかかったのが、スポンサー対策だった。
そう、日テレの経営はスポンサーの広告費で成り立つ。そのためには、一人でも多くの人にテレビコマーシャルを見てもらわないといけない。しかし当時、テレビを持つ世帯数はわずか866世帯。家族全員が見たところで数千人。到底、スポンサーは納得しない。
そこで、正力松太郎はある奇策に出た。
街頭テレビという発明 当時のテレビは1台17万円(今の物価なら約500万円)もした。一般家庭ではまず買えない代物だ。そこで正力は自費でテレビを100台購入し、都内の繁華街の広場に設置した。いわゆる「街頭テレビ」である。
これなら、街頭で見てくれた人々を視聴者としてカウントできる。1台につき1000人が見てくれたら、100台で10万人だ。この数字ならスポンサーにも、なんとか示しがつく。
開局2日目、早速それを試すチャンスが訪れた。後楽園の「巨人×阪神」戦の中継である。試合が始まると、街頭テレビに観客が殺到した。正力の目論み通りだった。
これに気を良くした日テレは、スポーツのビッグイベント中継を次々に仕掛けた。同年10月27日には初のボクシング世界フライ級タイトルマッチ「白井義男×テリー・アレン」戦を中継。この時はかつてないほど街頭テレビに人々が殺到し、あまりの混雑に都電がストップしたという。
極めつけは、翌54年2月19日から3日間行われた、日本初のプロレス中継。力道山と木村政彦のタッグが、シャープ兄弟と対戦した。多くの人々が都内の街頭テレビの前に群がり、新橋に設置された街頭テレビに至っては、実に2万人もの群衆が殺到したという。
正力は街頭テレビの前に大衆を集めることで、民放テレビの価値をスポンサーに理解させることに成功したのである。
ハプニングだらけの黎明期 今でこそ日テレはグループ合わせて社員数4000人を超える大所帯だが、開局当時は社員100人ほどの小さな会社だった。建物も平屋が1つ。NHKやTBSのようにラジオを経験せず、いきなりテレビ放送を始めたので、スタジオも小さいのが3つだけ。カメラに至っては2台しかなかった。
それだけに、今では考えられない笑い話のようなハプニングも多発した。
例えば、30分の歌番組を15分と勘違いして、15分用の台本しか用意しておらず、途中でそれに気が付いたADが急遽スーツを着て司会者に扮してアドリブでつないだとか、バックダンサーに進駐軍に出入りしていた踊り子を仕込んでおいたら、リハーサルは服を着て踊っていたのに、本番になったら裸で出てきたとか――。とにかく、黎明期のテレビ放送はハプニングの連続だった。
俗に言う、神話の時代である。
登場、井原高忠 日本テレビはアメリカのGHQの要請で作られた経緯もあり(ちなみに、開局時に暗躍した柴田秀利氏は後に日テレの専務になった)、アメリカのテレビを手本にした。かの国のエンターテインメントといえば、いわゆるショー・ビジネスである。日テレもその路線を踏襲した。
ここで、日テレの歴史を語る際に忘れてはならない人物がいる。井原高忠である。かの三井財閥の三井家の分家にあたる、井原家の御曹司。慶応大学時代の53年、まだ開局前の日テレで働きはじめ、その後、入社する。親戚に朝日新聞の村山社主がおり、日テレの編成局長も朝日新聞から出向で来ていたので、そのツテだった。
そう、驚くことに開局時の日テレの首脳陣は、読売新聞だけでなく、朝日新聞と毎日新聞の三社体制で構成されていた。正力松太郎の方針は「新聞は新聞、巨人軍は巨人軍、テレビはテレビ」だったのだ。
ヴァラエティ・ショーの時代 井原高忠サンが配属されたのは音楽班だった。現在、テレビ局の音楽班というと、音楽番組を担当する部署を指すが、当時の音楽班は“ヴァラエティ”を担当した。
そう――ヴァラエティ。現在のバラエティ番組とは若干意味が異なる。いわゆるアメリカナイズされた、歌とダンスとコントで構成されるヴァラエティ・ショーのことである。黎明期の日テレはこの“ヴァラエティ路線”で一世を風靡するが、その中心にいたのが、井原サンだった。
井原サンが演出して最初に人気を博した番組が、1958年スタートの『光子の窓』である。当時の人気若手女優・草笛光子を司会に、歌ありコントありの日本初の本格的ヴァラエティ・ショー。もちろん生放送である。オープニングで窓から顔をのぞかせてテーマ曲を歌う草笛サンの姿が印象的だった。
ちなみに、カメラが草笛サンの顔に寄っている間に、窓のセットが2つに割れて左右にハケて、衣装さんが草笛サンの服を着替えさせ、カメラが引くと――草笛サンが何もないスタジオの真ん中で別の衣装で歌い踊る演出は井原サンの発明である。
『光子の窓』から派生した2つのヒット番組 『光子の窓』の功績は、日本にヴァラエティ・ショーを根付かせたことである。それは、かの番組から2人の傑物が巣立ったことからも分かる。
一人は、同番組で井原サンの下でADを務めた「秋チン」こと秋元近史サン。もう一人が、同番組の構成作家を務めた永六輔サンである。
秋元サンは『光子の窓』の終了後、同じ日曜夕方の枠で、ディレクターとして『シャボン玉ホリデー』を開始する。時に1961年。ご存知、ザ・ピーナッツやハナ肇とクレージーキャッツらナベプロ(渡辺プロダクション)所属の歌手たちを一躍スターダムに押し上げたヴァラエティ・ショーの金字塔である。最高視聴率32.4%。11年間の平均視聴率は20%にも及んだ。
同番組から植木等の「お呼びでない?」をはじめ、数々のギャグが生まれ、また構成作家の青島幸男サンも一躍人気者になった。
一方、永六輔サンは少々経緯が複雑だ。1960年、永サンは安保闘争のデモに参加し、『光子の窓』の台本を落としてしまう(書かなかったという意)。井原サンは怒り、永サンを切った。困った永サンがNHKに仕事を求め――そこで書いたのが、同局の伝説的ヴァラエティ『夢であいましょう』である。
出演は、黒柳徹子に坂本九、渥美清ら。司会をデザイナーの中嶋弘子サンが務め、彼女の右に傾けてお辞儀をする挨拶が評判になった。同番組から『上を向いて歩こう』や『こんにちは赤ちゃん』など数々のヒットソングが誕生した。
巨人軍の誕生 ここで、話をプロ野球に転じたいと思う。
言うまでもなく、日テレといえば、読売ジャイアンツである。どちらも読売新聞社主・正力松太郎が始めた事業で、いわば兄弟の関係に当たる。
読売ジャイアンツが生まれたのは、戦前の1934年である。先にも述べたベーブ・ルースら大リーグを招聘して、親善試合を行うために結成されたチームが元になった。このチームが東京巨人軍となり、36年、日本初のプロ野球のリーグ「日本野球連盟」が誕生する。参加したのは巨人の他に、大阪タイガース(現・阪神タイガース)や名古屋軍(現・中日ドラゴンズ)など7球団。戦前、巨人は6連覇の偉業を達成するが、当時の野球人気の中心は大学野球。プロ野球の人気は低かった。
戦後、プロ野球は再開されるが、引き続き、人気は大学野球に遠く及ばなかった。そうこうするうちに日本テレビが開局。そして、ある事件が起きる。
『何でもやりまショー』で出入り禁止に 黎明期の日本テレビに、『ほろにがショー 何でもやりまショー』という人気番組があった。司会は三國一朗。一見、無茶なお題に挑戦する企画で、今でいうチャレンジものの走り。事件が起きたのは1956年11月3日だった。
その日のお題は「早慶戦に、早稲田側の応援席で慶應の大旗を振って応援した人に5000円を進呈する」というもの。ところが、これが大問題に発展する。放送終了後、日テレに視聴者からの抗議が殺到。事態を重く見た東京六大学野球連盟は、日テレに出入り禁止を通告する。
また、評論家の大宅壮一がたまたまこの番組を見ており、週刊誌に批判記事を発表した。その時のタイトルが、かの有名な『一億総白痴化』である
かくして、当代人気の六大学の野球中継ができなくなった日テレ。だが、時代は日テレに味方する。それは、一人の男によってもたらされた。
長嶋茂雄である。
ON人気で巨人戦がドル箱に 1957年秋季の東京六大学野球。立教大学4年の長嶋茂雄は、当時の新記録となる大学通算8本塁打を放ち、首位打者に輝いた。そして同年11月、読売ジャイアンツに入団する。
翌58年、プロ野球選手となった長嶋はデビュー戦で国鉄スワローズ(現・東京ヤクルトスワローズ)のエース金田正一に4打席連続三振を喫するも、この年、本塁打王と打点王の2冠に輝き、チームの優勝に貢献する。そう、長嶋時代の幕開けである。そして、その恩恵を最も受けたのが、巨人戦を中継する日本テレビだった。
時代は、大学野球からプロ野球へ、人気がシフトしようとしていたのである。
その流れを決定づけたのが、長嶋のプロ2年目――1959年の天覧試合である。
6月25日、後楽園球場で行われた大阪タイガースとの一戦。昭和天皇が観戦する中、長嶋はチームメイトの王貞治と共にホームランを放った。ON(オーエヌ)砲第1号である。さらに9回裏、村山実投手からサヨナラ本塁打。劇的な幕切れに、国民が熱狂した。
かくして、プロ野球の人気は大学野球を凌駕。以後、長きにわたり、巨人戦のナイター中継は日本テレビのドル箱になる。
![]() ヴァラエティの進化
ヴァラエティの進化 さて、話をヴァラエティに戻そう。
1965年、かの井原高忠サンが新番組を企画する。それは、日本初の複数作家制による合作スタイル――坂本九司会の『九ちゃん!』だった。番組作りのモデルとしたのは、アメリカの人気番組『ダニー・ケイ・ショー』である。
それまでテレビの台本は、複数の作家が持ち回りで書くものだった。それを井原サンはアメリカのスタイルに習い、共同作業にしたのだ。クオリティが保たれ、締切が守られる利点がある。今日では当たり前の手法である。
この時の作家が、小林信彦サン、井上ひさしサン、河野洋サン等々。皆、一流の作家ばかりである。これに先だって、井原サンが井上ひさしサンを引き入れようと口説いた台詞が面白い。井原サンはブロードウェイで活躍する大作詞家の名前を出して、こう言った。
「あなたは日本のオスカー・ハマースタイン二世になるおつもりはありませんか?」
井上サンは二つ返事で引き受けたという。
麻布プリンスホテルにて 同じ時期、井原サンは、それまでにない、全く新しい番組も立ち上げようとしていた。
時に1965年夏、今はなき麻布プリンスホテルのプールで、井原サンは前田武彦サンと落ち合った。新番組の企画の相談である。
前田武彦――前武サンは放送作家出身の司会者である。秋チンこと秋元近史サンがディレクターとして一本立ちした『魅惑の宵』の台本を書いたり、『シャボン玉ホリデー』のテーマソングなどを作詞した。今日のバラエティ用の台本(原稿用紙の真ん中に線が引かれ、上にカメラの画、下に台詞を書く)を考案したのも前武サンと言われる。
そんな前武サンに、井原サンはこう切り出した。
「実はね、夜遅い時間でナマのワイドショーをやりたいんスよ」
ターゲットは男性層 それまで、ワイドショーといえば朝か昼のものだったのを夜遅くにやるという。しかも、ターゲットは男性である。モデルはアメリカの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー』らしい。
前武サンは思いつくままにアイデアを出した。できることなら、自分が司会をしたいとも付け加えた。井原サンはしばらく黙って聞いて、笑顔で礼を言って帰った。
11月、かつてない新番組が始まった。オープニングでジャズのスキャットが流れ、バニーガールがスタジオを彩る。コンセプトは男のダンディズム――。
『11PM』である。
前代未聞の『ゲバゲバ90分!』 そんな『11PM』が軌道に乗って3年目。井原高忠サンは、またまた新たな番組を企画しようとしていた。しかも今度のヤツは、かなりスケールが大きいという。
モデルとしたのは、当時アメリカで話題になっていた『ローワンとマーティンのラフ・イン』である。短い“サイト(視覚的)ギャグ”が洪水のように流れ、合間に司会のローワンとマーティンの軽妙なトークが入る。ところどころにジョン・ウェインなどの大物スターが登場して「サッカ・トゥ・ミー」と意味不明な単語を叫ぶと、画面外から笑いが聞こえる――というのが基本フォーマット。
これを日本流にアレンジして生まれたのが、かの有名な『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』だった。
当時、大橋巨泉と前田武彦は、テレビ界の人気を二分する超売れっ子司会者。巨泉サンが『11PM』や『お笑い頭の体操』(TBS)など週5本、前武サンが『夜のヒットスタジオ』(フジ)や『お昼のゴールデンショー』(フジ)など週6本のレギュラーを抱えていた。この2人が競演する――まず、それが前代未聞だった。
130本のコント、台本の厚さ2㎝半 ――加えて、共演は当代人気随一のコメディアンのコント55号。他に、小松方正、宍戸錠、常田富士男、藤村俊二、大辻伺郎、熊倉一雄、朝丘雪路、松岡きっこ、小川知子、うつみ宮土理、吉田日出子、ジュディ・オング、ハナ肇――と人気スターが集結した。コメディアンではなく、俳優主体で臨んだのは、“既存のヴァラエティにしたくない”という井原流のこだわりだった。
何より前代未聞は、その予算である。番組1本1,500万円。これは現在の物価に換算すると4,500万円ほど。ドラマの倍近くだ。さらに90分間に作られるコントは130本、構成作家は総勢42人。台本の厚さは2㎝半に及んだという。
初回放送は1969年10月7日、視聴率は26.2%だった。放送翌日、小学生たちが学校でハナ肇の台詞「アッと驚くタメゴロー」を連発したという。
前代未聞の番組は、大成功だった。
![]() テレビ界の不文律
テレビ界の不文律 テレビ界には昔から不文律がある。同じ時間帯の裏番組に出ないこともその1つ。スポンサーへの配慮である。昔はもっと厳しくて、同じプロダクション同士が裏表に出るのもタブーとされた。
1973年、その不文律がキッカケとなり、大問題が起きようとしていた。世に言う「日テレvs.ナベプロ」戦争である。
事の次第はこうである。当時、月曜夜8時台に放送中の『NTV紅白歌のベストテン』と同じ時間帯のNET(現・テレビ朝日)で、渡辺プロダクションによる新人発掘の歌番組の企画が進んでいた。これが始まると、『紅白歌~』にはナベプロの歌手は出られなくなる。当時のナベプロは人気歌手を多く抱える“ナベプロ帝国”。そうなると、日テレの歌番組が成り立たなくなる恐れがある。
そこで、当時、制作局次長に昇進していた井原高忠サンが、日テレを代表してナベプロへ出向き、渡辺晋社長と直談判した。なんとか再考してくれないか――と。だが、ここで晋社長がテレビ史に残る言葉を口にする。
「だったら、『紅白歌のベストテン』が放送日を変えればいいじゃないか」
ナベプロと決裂す ――それが引き金だった。井原サンの表情が一変する。
「じゃあ結構。もうお宅の歌手はいりません! その代わり、金曜日の夜、渡辺プロにあげようと思ったワクもあげません!」
そう言い放ち、席を立った。
社に戻ると、井原サンはナベプロ以外の全芸能プロダクションの社長を招集した。
「実はカクカクシカジカの事情で、渡辺プロと決裂した。正直、困っている。だから助けてほしい。ここは一つ、井原を男にしてくれ――」
そう言って、深々と頭を下げた。
かくして、日テレは当時、新人発掘番組として売り出し中の『スター誕生!』から、新人スターをホリプロやサンミュージック、田辺エージェンシーら新興プロダクションに配分する見返りとして、『紅白歌のベストテン』への全面協力を取り付けた。
ナベプロの落日と天才の死 さて、そんな次第で、NET(現・テレ朝)ではナベプロ制作の新番組が始まるが、視聴率は思いのほか低迷。わずか2クールで終了する。それを機に、ナベプロは徐々に芸能界における影響力を低下させていく。
一方、前述の金曜夜の枠は、和田アキ子にザ・デストロイヤー、せんだみつおらを起用して、73年10月『金曜10時!うわさのチャンネル!!』と銘打ってスタートする。日テレは全社一丸でこの新番組に取り組み、最高視聴率27.6%を記録する。同番組の成功は、ナベプロ抜きでもお笑い番組が成立することを証明した。
だが、喜んでばかりもいられなかった。この“戦争”の煽りを受けた一人の男がいた。『シャボン玉ホリデー』をはじめ、それまで長くナベプロとの蜜月関係を築いた秋チンこと秋元近史サンである。社内が“反ナベプロ”で固められて以降、次第に居場所を失っていった。
その心労がたたり、82年、出向先の日本テレビの子会社のビルから飛び降りる。享年49。天才ディレクターの早すぎる死であった。
かつての日テレのドラマたち ここで、1960~70年代の日テレのドラマについても触れておきたい。
有名なのは、東宝が手掛けた一連の青春ドラマだろう。65年の夏木陽介主演の『青春とはなんだ』(ちなみに原作は石原慎太郎の同名小説)を皮切りに、『これが青春だ』、『でっかい青春』、『進め!青春』――等々と続くシリーズ。かと思えば、松竹の制作する森田健作の『おれは男だ!』シリーズもあった。中村雅俊の『俺たちの旅』に始まる“俺たち”シリーズも。いずれも日曜8時枠だった。
もう一つの系譜は、水曜8時枠。こちらは石立鉄男主演・ユニオン映画制作の『おひかえあそばせ』、『気になる嫁さん』、『パパと呼ばないで』、『雑居時代』――と続く一連のシリーズだ。脚本は松木ひろし。コメディ形式のホームドラマを確立し、この路線は、後に同じ松木サン脚本の『池中玄太80キロ』に受け継がれる。
『太陽にほえろ!』から巣立ったルーキーたち 1970年代、映画会社が制作するドラマが飛躍的に増えたのは、日本の映画界が斜陽になったからである。彼らはテレビに活路を見出すしかなかったのだ。
その中でも、最も成功したドラマが、東宝が1972年に日テレの金曜8時枠で始めた『太陽にほえろ!』だろう。足掛け14年も続いたのは、石原裕次郎演ずるボスが主役ながら、事実上の主人公を若手刑事役のルーキーが務めたこと。彼らは殉職すると、また次の新人刑事が入ったので、視聴者は飽きずに楽しめたのだ。
ちなみに、殉職した後、ルーキーたちは同じ日テレの他のドラマで主演を務めた。ショーケン(萩原健一)が『傷だらけの天使』に『前略おふくろ様』、松田優作が『俺たちの勲章』に『探偵物語』、勝野洋が『俺たちの朝』、沖雅也が『俺たちは天使だ!』――等々。
中でも、最も印象に残るのは、やはりあのドラマだろう。
『傷だらけの天使』という伝説 1974年10月5日。時の総理・田中角栄が退陣する原因となる『文藝春秋』11月号が発売される4日前、伝説のドラマは幕開けた。
ファーストカットは黒味にタイトル。やがて画面が白み、一人の男が浮かび上がる。水中ゴーグルにヘッドフォン。男は長い脚を上げてベッドから起き上がると、冷蔵庫の扉を開け、新聞紙をナプキン代わりに、トマトやコンビーフ、魚肉ソーセージなどにかぶりつく――かの有名な『傷だらけの天使』のオープニングである。カメラマンは木村大作、音楽は井上堯之バンド、衣装は菊池武夫が担当した。
![]()
主演は萩原健一である。相棒役に水谷豊。他に、岸田今日子や岸田森ら個性派俳優たちも共演した。メインライターを市川森一が務め、深作欣二をはじめ、映画界から神代辰巳や工藤栄一、恩地日出夫といった第一線の監督たちが参加した。
そのヌードや暴力シーンも辞さないアバンギャルドな作風は若者たちの心を捉えるが、同ドラマはテレビ界のどんな賞ももらわなかった。視聴率も一度も20%に届かなかった。
最終回、水谷豊演じる亨は風邪をこじらせ、肺炎で死ぬ。視聴率は19.9%。その4年後、水谷は同局の『熱中時代』の最終回で視聴率40%を達成する。
亨のリベンジだった。
70年代後半の日テレ ここから先の話はあまり長くない。
1970年代後半、日テレは民放キー局の中で視聴率2位を堅持するも、長くトップに君臨するTBSには追いつけないでいた。
井原高忠サンは78年に第1制作局長となり、現場から離れた。気が付けば、かつてのヴァラエティ・ショーは日テレから姿を消し、局としての独自色が失われようとしていた。日テレは次の一手を模索していた。
そんな時、1つのスペシャル番組が産声を上げる。奇しくも、王貞治選手がホームランの世界新記録756号を放った翌日、同じ後楽園球場で番組収録が行われた。『第1回アメリカ横断ウルトラクイズ』である。
この日、予選に参加したのは404人。司会は同局のアナウンサーの福留功男。第1問は「上野動物園のパンダの名前はリンリン、カンカンである」だった。
![]()
同番組は、その年の10月下旬に放送され、20%超えの高視聴率を獲得する。そして以後、毎年開催されるようになったのは承知の通りである。
何より画期的だったのは、同番組には元ネタがなかったこと。完全に日テレのオリジナルだった。参加人数、移動距離ともクイズ番組として世界に類がなく、後にアメリカとイギリスのテレビ局がフォーマットを購入して、自国版を制作したほどである。
そして最も特徴的だったのは――クイズ番組といいつつ、その実態は人間ドラマだったこと。このノウハウが、後に日テレの“復活”に生かされることになるが、まだ、この時は誰も気づいていない。
80年代へ 1980年6月、井原高忠サンはかねてから決めていた50歳を節目に、日テレを退職する。
かつての日テレの自由な社風が失われつつあり、読売新聞色が強まっていたことも理由の一つだった。1975年の“腸ねん転の解消”で、日本の民放キー局は新聞社との系列関係を強めていた。クロスオーナーシップである。
そして、井原サンが退職する前月、奇しくもフジテレビが大改革を行い、弱冠42歳の日枝久サンが編成局長に就いた。それを機に――80年代、テレビ界の地図は大きく変動する。フジとTBSは激しいデッドヒートを繰り広げ、日テレはその間に埋没し、かつてない低迷期を迎えるのだ。
日テレの暗黒時代が、静かに忍び寄ろうとしていた。
だが、笑顔で退職記念の花束をもらう井原サンは、まだそのことを知らない。
(後編へつづく)
(文:指南役 イラスト:高田真弓)
【関連記事】
【絶狼で再共演】弓削智久と芳賀優里亜が振り返る 仮面ライダー龍騎&555の時代
vol.2.5 ホーム・アローンでジョー・ペシを知った 〜 映画監督を志すまで 〜
「自分を客観視できてないからアナタは童貞」SNSを使って女を抱く方法をインターネット文化人類学者が語る
vol.2 「や」さん 〜告白されて、恋を知る〜 後編
元記事のURLはこちら
http://social-trend.jp/33755/















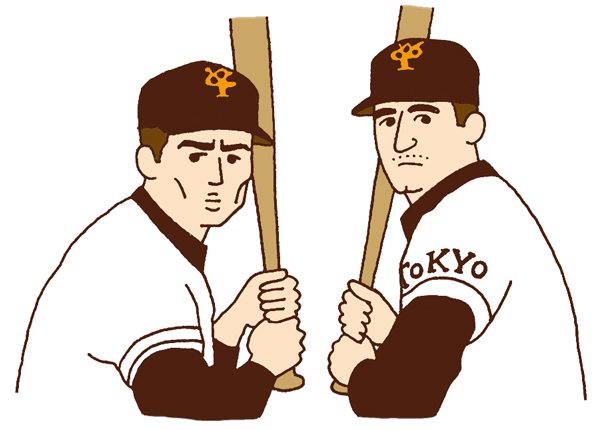



 ミネラルカラー。
ミネラルカラー。
 ミネラルカラーの使用イメージ。近年主流となっているホワイト基調のオフィスインテリアとも自然にマッチします。
ミネラルカラーの使用イメージ。近年主流となっているホワイト基調のオフィスインテリアとも自然にマッチします。
 こちらはカーボンカラー。
こちらはカーボンカラー。
 カーボンカラーの使用イメージ。
カーボンカラーの使用イメージ。
 グラファイト。アーロンチェアといえばこれ、の象徴的なカラーです。
グラファイト。アーロンチェアといえばこれ、の象徴的なカラーです。
 グラファイトの使用イメージ。
アーロンチェア リマスタード
グラファイトの使用イメージ。
アーロンチェア リマスタード








